
本物の感動と満足を味わっていただけるように皆様からいただいたお声と私たちの経験を最大限に生かし作り上げた旅、それが「夢の休日」です。
目に見えないクオリティーの追求こそ大切と考え、素材一つひとつを吟味し作り上げた“心を込めた上質な旅”をお楽しみください。
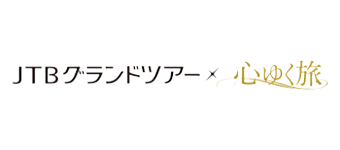
パッケージツアーでありながら、まるで個人旅行のように自由で、アットホームな海外旅行。
この旅を実現するために、旅に精通した添乗員とおもてなしの心を持ったロイヤルロード銀座のスタッフが一丸となってお手伝いします。
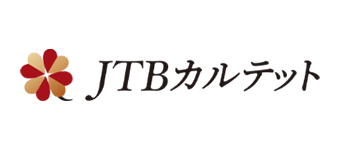
テーマあるゆとりの旅をコンセプトとする海外ツアーブランド、“JTBカルテット”。企画から販売、手配、アフターケアに至るあらゆる場面において、心のこもったサービスをモットーにしております。

JTBロイヤルロード銀座特別企画や予約が取りにくい名店でのお食事など、とっておきのひとときをお愉しみいただきます

ゆったりと贅沢に国内旅行を楽しみたい方のためにご用意した少人数ツアー“夢の休日”。日本の美しい四季や各地の伝統行事、旬の味覚や郷土料理などをゆとりあるスケジュールでご案内いたします。

美術・音楽を愉しむ旅、講師同行の旅、島旅などテーマ性の高い旅❝四季彩紀行❞。「煌」や「夢の休日」とはひと味ちがうはじめての感動体験やその土地ならではの景色をお愉しみいただきます。

オーダーメイド旅行の目的、価値観、こだわりは人それぞれ違います。あなただけの専属担当があらゆるご希望を汲み取り、関係機関と連携しながら、お客様とつくりあげていく“最高の旅”。お客様の想いが形になった旅行、それがロイヤルロードです。どうぞあなたの旅への想いをお聞かせください。世界にたったひとつの旅をあなたに。

高品質な日本国内のご旅行をご提供する「グローバルラウンジ銀座」。「海外から大切なお客様をお迎えしたい」、大切なお客様の日本国内の移動手段、宿泊施設の手配、日本文化の体験など、あらゆる旅のお手伝いをいたします。

国内旅行から世界一周旅行まで、クルーズのことならJTBへおまかせ!クルーズ専門スタッフがカジュアル客船から超豪華客船までお客様のニーズに合わせた船の旅をご提案致します。

琥珀色の古都を訪ね、バルト海クルーズも楽しむ

スペインの大聖地サンチャゴ・デ・コンポステーラにも宿泊

アメリカ西部6つの造形美を愉しむ

2都市で各3連泊 ブリュッセル・アムステルダム
豪華列車ハイラム・ビンガム号に乗る
ビジネスクラスの旅
北緯64度 北極圏の大自然とオーロラを愉しむ
クルーズ船「ソネスタ・サンゴッデス号」で巡る壮大な遺跡群

ヨーロッパ92の都市とつながる「KLMオランダ航空」。歴史のある航空会社として、…

通常の大型バスにわずか10席を配置したラグジュアリーバス「ロイヤルロード・プレミ…

海外旅行にとって航空機での移動はとても重要なポイントです。特に長時間になるヨーロ…

~音楽が彩る感動のひとときをあなたに~ その時、その場所にいた方だけが体感できる…

あなたが旅行で楽しみたいものは何ですか?雄大な自然風景、歴史ある街並みや伝統文化…

海外旅行では“機内でいかに快適に過ごせるか”はとても重要なポイントです。特に長時…

移動時間の長いヨーロッパへの旅行。「長時間のフライトを快適に過ごしたい!」と多く…

ロイヤルロード銀座のコンシェルジュは、お客様のご要望をお伺いし、喜んでもらえるご…

皆さまこんにちは。JTBロイヤルロード銀座で主にラグジュアリーバス「ロイヤルロー…
2024.04.25

こんにちは、添乗員の龍谷です。6/1(土)出発 コルドバ・グラナダ・マラガ8日間…
2024.04.18

みなさまこんにちは。国内企画担当の小寺です。『夢の休日・四季彩紀行』の夏秋号が完…
2024.04.11

皆様こんにちは。海外企画担当の宮嶋です。早いもので今年も4月に入り2024年度が…
2024.04.05
お客様お一人おひとりのご要望をじっくり伺い、最適な旅のご提案をさせていただくために、JTBロイヤルロード銀座では、ご予約制のゆったりとしたサロンで、コンシェルジュがご相談を承ります。
また、ツアーの企画部門も併せ持ち、経験豊かなツアープランナーが生み出す高品質パッケージツアーも豊富なラインナップ。
コンシェルジュを通じて届くお客様の声から生まれたツアーは、旅慣れた方にもきっとご満足いただけることでしょう。
詳細を見るロイヤルロード銀座の各店舗をご案内します。
店舗情報・アクセスをみるパンフレットではお伝えしきれないポイントや現地情報をご案内する旅行説明会や、旅を便利に・楽しくする製品やサービスを提供している企業との共同開催イベントなどを開催しています。
イベント情報をみるご旅行に関するお問い合わせ・ご質問を承ります。お近くの店舗までお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせ